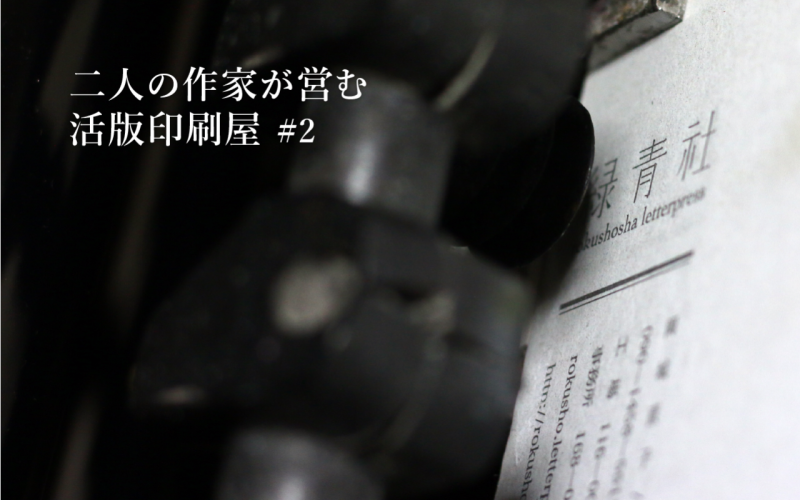#職人

活版印刷を愛する人々が集う共同作業室が、西武多摩川線・新小金井駅すぐの場所に誕生しました。名前は溝活版分室。様々なものがシェアされる世の中になりましたが、活版印刷の世界においてはあまり聞き慣れない、この分室という名のついた場所は、どのような経緯と想いの中で生まれたのでしょうか。メンバーである横溝さん、加賀美さん、津村さんの3名にお話しを聞きました。

東久留米市で昭和42年から続く細田木工所の3代目、細田真之介さん。いま彼が目指しているのは、まちづくり会社の設立。家具職人として木工所のしごとに実直に取り組む細田さんは、なぜ“まち”へと視線を向けたのでしょうか。

バイオリンの修理や調整で、お客さんが引きも切らない岩崎工房。昔からモノづくりが好きだったという主宰の岩崎さんが、バイオリン職人として独立し、遠く海外からのお客さんも訪れるという人気工房になるまでの道のりとは…?

オーダーメイドの手製本や製本教室を行なっている空想製本屋の本間あずささん。この秋、新小金井駅の駅前に新しいアトリエを構えました。2010年に会社勤めを辞め、製本をしごとにすると決意してから8年。自らの城を持つまでの道のりと、本間さんの背中を押したきっかけをお聞きします。

電動車いすを改造するという、世間一般的に知られていない業界に足を踏み入れ、はたらくことを選んだ車いす工房 輪の浅見一志さん。会社員から経営者へ。これからの福祉業界を豊かにするための持論と想いを伺います。

電動車いすは、どんな人に必要なのか。 それを明確に説明できる人がどれくらいいるのでしょうか。ましてや、電動車いすを改造するというしごとは、ほとんどの人に知られていない職種です。このしごとに使命を感じて起業を果たした、車いす工房 輪の代表・浅見一志さんの物語をお届けします。

生涯を通して添い遂げたいと想える存在があったとき、その実現のためならば、私たちは自分なりの道を見つけながら前向きに歩み続けられるのではないでしょうか? そんなことを教えてくれたのは、今回の主役である山田亜紀さん。これは、現在、東京藝術大学大学院の研究室で仏像修復に携わる彼女の成長の物語。

一冊の本から“手製本”という文化があることを知り、空想製本屋という屋号で活動をスタートさせた本間あずささん。スイスの製本学校で手製本の技術と知識を学んだ後、日本で製本家として唯一無二の本を作り、届ける彼女の今までとこれからについて詳しく伺いました。

製本家として、本と人とを繋ぐしごとをする空想製本屋の店主・本間あずささん。たかが本されど本。一冊の本が、はたらきかたを、時には人生そのものを変えるバイタリティを持つということ。前編では、本間さんと手製本との出会い、製本家として生計を立てるまでの道のりについてです。