地域で看取る穏やかな最期の日

厚生労働省によると、1950年以降、自宅で人生の最期を迎える人はコロナ禍などを除いて年々減少し、現在では、6割以上が病院や診療所で亡くなっています。自宅は2割以下になっていますが、一方で、治る見込みのない病気で死が近いなら「自宅で最期を迎えたい」と考える人は4割以上。暮らしや家族のあり方も大きく変化する中で、わたしたちの“死に方”はどうなっていくのでしょうか。自分が望む死の迎え方は実現できるのか。全国的にもめずらしい一軒家を改装した住宅型有料老人ホームで、訪問看護ステーションでもある「はじまりの家そら」を訪ね、代表で看護師の冨澤文絵さんにお話を聞きました。
日常の中に“死”がある
「“生き様が死に様”っていう言葉がありますよね。本当にその通りで、人は生きてきたように死んでいくのだと日々感じます」
看護師として、数多くの看取りの現場を目にしてきた冨澤さんはそう語ります。
「昔の人は、日常の中に人の死があるという状況が当たり前でした。けれど、社会のあり方も家族や家のあり方も随分と変わりましたよね。子ども時代、わたしはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らして、家でお葬式をしたことを覚えています。家から出棺して、近所の人たちが割烹着を持って手伝いに来てくれて。そういう人生の終わり方を見た、ほとんど最後の世代かもしれません。黒い服を着て、みんな泣き顔で終わりではなくて、ある意味では宴会的にわいわいとお別れする。あの雰囲気がわたしは好きだし、それでいいんだと思ったんです」

自分の死生観を形作った原体験に背中を押されるように、冨澤さんは「こういう死に方があるんだ」と思える最期の迎え方を提示していきたいと考えています。
「“死の概念”というと少し大袈裟かもしれませんが、現在の日本は死を遠ざける傾向があって、特別扱いしすぎていると感じます。家で最期を迎える方々の看取りに訪問看護で携わっていると、死って本当に自然なことだと感じます。自然であることをもっと意識してほしいし、“死に至る過程を看る”という経験をして、実感してほしいと思います。家族や友達の死も、自分の死も、いつも通りの日常の時間の流れの中にある。そういうイメージを持てたらいいなと思うんです。今って、『病院で死ぬんだ』って想像している人が多いですよね。イメージしたものは現実に下ろされやすくなるので、違う死のあり方を伝えたい。一度崩れた“日常の中の死”を、わたしは改めてつくっていこうとしているんだなと思います」

現実問題、“家で看取る”が叶わない
在宅で最期を迎えるためには、死亡確認をして、診断書を書くという役割のために、訪問診療という形で必ず医師が関わります。訪問看護師は、日常生活を送る上で必要なケアを担い、家族とともに一番近くで携わる存在です。
「医療的な処置がいる場合でも、一人暮らしであっても、家で最期を迎えることって、多くの方が思うより可能なんですよ。病院でできて、家でできないことはないといってもいいくらい。逆に病院でできないことは沢山ありますけど(笑) 訪問看護の回数を増やしたり、公的なサービスを調整して、見守りとしてそばにいる人を確保すれば、在宅での療養と看取りは十分に対応できる。だって、死は自然なことで、本来なら医療の手に委ねる必要はないものです。けれど、実際には本人が家にいたいと言っても、周りが受け入れられなかったりするんですよね」
家で療養していた人にも、入院している人にも、いずれ終末期がやってきます。そのとき、どのようなことが起こっているのでしょう。
「ある日、岐路に立たされるわけですよね。どのような経過で終末期を迎えるかによっても違いますが、自宅での療養が難しいとなれば病院へ行き、病院でもできる治療がなくなると、医師からは『家に帰りますか、それとも』と訊ねられます。がんであれば、ホスピスとか緩和ケア病棟とか、療養のできる施設が選択肢として挙げられます。そのとき、『本当は家に帰りたいけど』『家で看取ってあげたいけど』と思ったとしても、次の瞬間には、『でもこの状態で帰っても大丈夫か』『でも仕事があるし』と次々と『でも…』が思い浮かびますよね。帰ったとして、そこで死を迎えることへの漠然とした不安と心配もあると思います。結局、『いや無理だよ』という感じで選択を決め、二度と家に帰ることはなくなってしまう人もたくさんいます」

「うちへどうぞ」と言える看取りの家
病院勤務の看護師としてキャリアをスタートさせた冨澤さんは、病院での看取りを目にする中で、純粋な疑問が常に頭に浮かんでいたといいます。
「『家に帰りたい』という気持ちを持ってらっしゃる方が多いのに、叶えられない。大変な治療を乗り越えた先にある最後の願いすら、口に出すことをためらっている様子がわかる。『病院って死ぬ場所としてどうなのかな』と感じていました」
2015年には、在宅での看取りに携わろうと中野区で訪問看護ステーションを開設。充実感を持って働いていましたが、「家がいいけど難しい」という人と接する中で、「うちにどうぞ、って言えたらいいのに」と考えはじめたそう。
「基本的には家でよくて、そのために必要な体制を整えるということも大事だと思います。一方で、建物的な問題や家族への遠慮、不安感が理由で家が難しいなら、そういう人に向けた場を持てるといいなと思ったんです」
2022年6月に東久留米の空き家を内見し、2023年の年明けには開所式。大急ぎで融資の手配をして、住宅型有料老人ホーム、訪問看護ステーションとして登録を受けるための申請も済ませました。
「『ここに来るだけでほっとする、元気になる』と思ってもらえる場所を目指しました。訪問看護をしながらいつも感じるのは、“住まいの環境”って本当に大切だなと。自然に癒されながら本来持っている力を発揮できる空間をつくっているので、ぜひいらして体感していただきたいです」


「はじまりの家そら」では、これまで3人の看取りを行なっています。
「お一人目のとき、その方が療養されている空間と壁1枚挟んだ部屋では、賑やかにイベントをしていたんです。近所の方が開いた整体講座でしたね。通常だったら、もう亡くなりそうな人がいる場所で賑やかにするなんてとんでもないという話になりますよね。死は、隔離された場所で厳かに迎えるものだという意識を、ひとつ取っ払えた気がしました。家で亡くなるときのご近所の日常の再現というか」
もうお一人は、訪問看護を利用しながら在宅療養をしていた方。ご家族が通いながらサポートしていましたが、次第に介護負担が大きくなり、そらへやってきました。
「いつ旅立たれてもいい状態だったので、娘さん二人も泊まられて、そばで見守られました。最期の日にはご親戚も集まってお別れをされて。滞在中、ご家族の方とそらのスタッフが一緒に朝ご飯を食べる時間もあって、思い出話をお聞きしたり、わたしたちにとってもすごくいい時間でした。心の準備を徐々にしていけるんですよね。亡くなる前からちょっとずつ、何気なくご家族へのグリーフケアもできる。ご本人とゆっくり触れ合える時間の先で看取りができると、『よかった』という満足感といいますか、『やりきった』という思いを感じていただけます」


「介護を通じて、あるいは終末期という特別な時間を通じて、それまで蓋をしてきた家族の問題が浮上してくることも多いです。“介護”そのものよりも、様々な感情が噴き出して『大変』と感じることもあると思います。そのことを介護のせいにするのではなく、携わる人それぞれの人生の棚卸しと捉えて、これまでの関係性の修復や、自分自身を振り返るきっかけになるといいなと思います」
これからの日本で、どこで死を迎えるのか
病院勤務、訪問看護、はじまりの家そらと、看取りに携わり続けてきた冨澤さん。この先、死のあり方や死を迎える場所はどうなっていくと感じているのでしょう。
「『家に帰りたい』と意思を伝える方は増えている気がします。これからは、よりはっきり分かれるかもしれないなと思います。帰りたい方ははっきりそう言うし、そうじゃない方は自分で決めること自体をしない。“終活”という言葉も生まれて、元気なうちから準備した方は強い意思を持ってそういう人生を組み立てていくでしょうし、『なるようにしかならないでしょ』という方は『周りにおまかせするわ』という生き方をされているのかもしれません。良い悪いはありません」

「想像するって、人間に備わったすごく大事な機能ですよね。世の中が今どうなっていて、暮らしている地域がどうなってるのかって見て、『はて、自分が死を迎えたい場所はどこだろう』と考える。わたしの場合は、今ここにはないなと思って『そら』をつくりました」
そう考える冨澤さんには、ひとつの危惧があります。
「社会のシステムがあまりにもきっちり作り上げられていて、現代人というか、わたしたちに、選択とか決断をできる力がある?ってちょっと感じるんですよ。例えば、仕事がすごく忙しいと、想像するとか、最大限いい選択をしようとか、できなくなってるじゃないですか。『本当はこうしたいのに』で終わっちゃうことも多いと思うんですね。どこで死ぬかって結果でしかなくて、瞬間をどう生きるのかがその後のすべてにつながっていく。どういう生き方をしたいかが、死に方にもつながる。実際どうなるかはわからないとしても、周囲に左右されたり、思い込みで諦めるんじゃなく、それまでの人生をかけて、最期の場所を選ぶとき、希望を言える自分、選択肢にない発想を思い浮かべられる自分、決断できる自分になれるように“選択できる力”を養っていくことが大事じゃないかと思います」
自宅である必要はないのかもしれない
「ここまでと話がひっくり返ってしまうかもしれないですが、『家がいいんだ』ということを、実はそらをはじめる前ほど思わなくなりました。人は変化を嫌う傾向が強いですし、例え自分にとって悪い選択肢だったとしても、同じところに留まっていたくて『住み慣れた自宅が一番!』だと言うでしょう。そう考えるようになったきっかけは、週末だけそらに泊まりに来られる89歳の方の存在です。『そらを利用するようになってから元気になった』と、ご家族もとてもよろこんでくださっていて。足のケアをして歩き方が安定したり、よく食べるようになったり、会話も弾むようになったり。そんな様子を見ていると、自宅そのものにこだわる必要はないんだという実感があります。自宅に帰りたい気持ちも大切にしたいですが、手放したら案外、むしろ世界が広がるかもしれない」

終末期を迎えた人から聞いた思いも振り返ります。
「終末期の方からよく聞くのが、自分の死をある程度覚悟しているので、『特別扱いしてほしくない』という思いです。自分がいるから楽しいイベントを中止にするんじゃなくて、いつも通りでいてほしいし、自分のこともこれまで通りに見てほしいって…。家に戻りたいという気持ちになるときに、どういう音が聞こえていてほしいか、見えてほしいか、どういう気持ちを感じていたいか。家に帰ってこれまで通り過ごすことが必ずしもゴールじゃなくて、その思いを叶えることに意味があると思うようになりました」
自宅ではなくても、日常の中にいると感じられる場所。はじまりの家そらの次なるビジョンです。

「そらをつくってから今まで、極端な話、何1つ思うようにはいかなくて、迷いと葛藤の2年間でした。ここまでは訪問看護ステーションに軸足を置いていましたが、ここからは、すべての世代の方にそらをご利用いただき、笑いと『ありがとう』があふれる場にしていきたいと考えています。その中で、心を込めて終末期の方の看取りをできるような体制を立てたいと思案しているところです」
理想の姿は、そらがモデルになり、全国のあちこちに同じような受け皿ができることです。
「地域のみんなで旅立ちを見送れるような場所にするのが、一番の役割かもしれません。わたしは“祝福死”というイメージを持っています。人間が持っている強さ、死に向き合う方の強さ、何より命は自分だけのものではないことを目の当たりにすると、学ぶことが多くあります。その経験を、自分だけに留めておくのが申し訳ないと感じるくらい、共有すべきだと感じるんです。悲しいだけで終わらせたらもったいない。いつも通り流れる日常の光景の中で、一人ひとりのかけがえのない人生が終わる姿に感謝を伝え合いながら見送りたい。そして、その姿を次の世代に引き継いでいきたいです」
自分はどこでどんな最期を迎えたいか、家族の死をどのように見送りたいか。周りに広がる日常の風景を眺めながら死に方を考えることは、今この瞬間からの生き方を考えることそのものであるようです。(國廣)
プロフィール
冨澤文絵
NPO法人コミュニティケア・ライフ理事。看護師として病院勤務、中野区内での訪問ステーション開設を経て、2022年、東久留米市にコミュニティホーム「はじまりの家そら」を開設。訪問看護ステーションとして市内を中心にケアを提供し、終末期のリトリート・ショートステイに特化した住宅型有料ホームとして看取りを含めて対応している。そら1階では金土曜日に「そらカフェ」を営業しているほか、臨床美術プログラムやマルシェなども開催。
コウカシタLAB 第1期メンバー募集
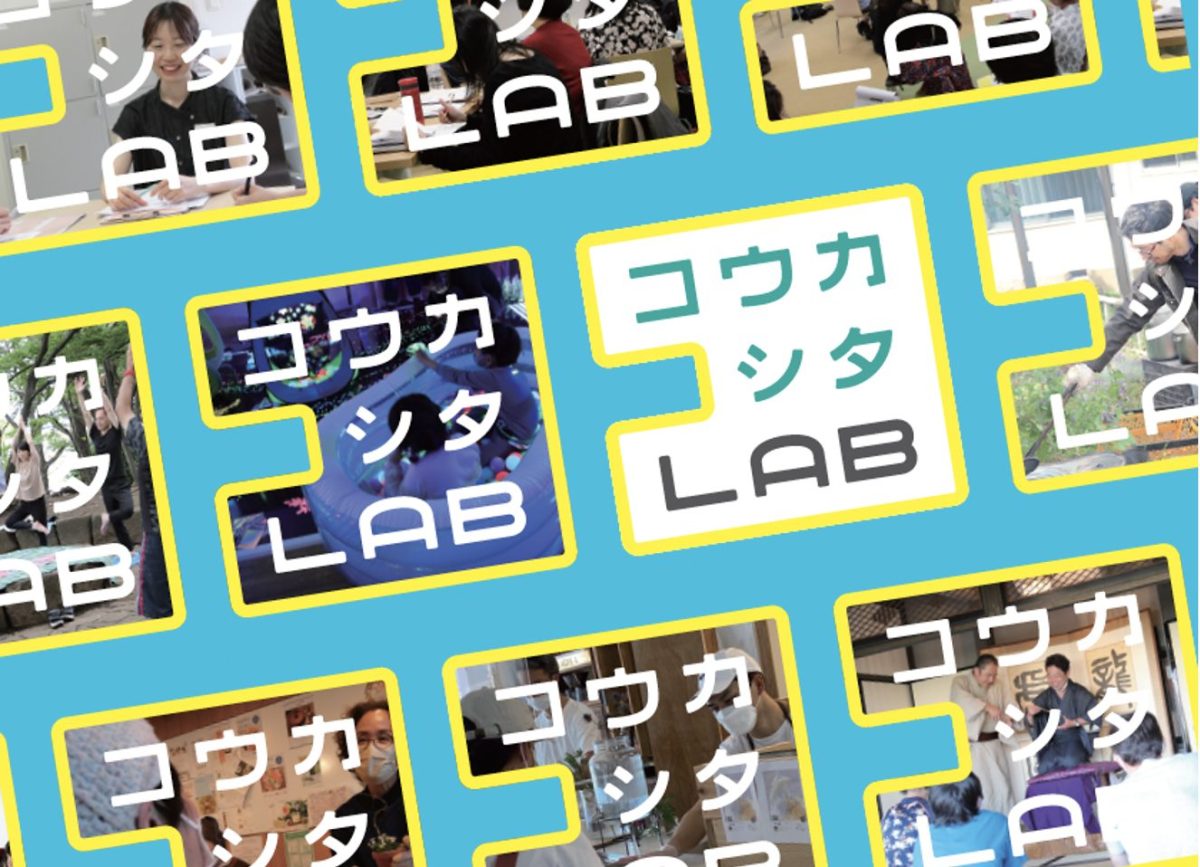
小さな実験が、まちを変える。
コウカシタLABは、一人ひとりの「やってみたい」を カタチにする実践型ワークショップです。カフェをひらく、教室をはじめる、イベントを仕掛けるー。学びと対話を重ねた最終回には、コウカシタパークのショップや広場を利用し、自分のアイデアをトライアル。2014年から続く「コウカシタスクール」 「まちのインキュベーションゼミ」が新たにLABとしてリニューアル。
面白いまちは、自分たちでつくる時代。さあ、実験をはじめよう!
- 期間
2025年11月29日(土)〜2026年3月7日(土)
- 場所
コウカシタパーク(JR中央線東小金井駅より徒歩5分)
- 定員
18名
- 参加費
8,800円(税込)
- こんな方におすすめ
・まちをフィールドに、プロジェクトをはじめたい
・自分のスキルを活かして、新たな仕事をつくりたい
・共に活動する仲間と出会いたい
・地域課題の解決に向けたアクションを起こしたい
・既存の活動や事業の幅を広げたい- プログラム
第1日目 オリエンテーション
11月29日(土)14:00-18:00
ぼんやりとした想いも、形になりかけたプランも。自分のアイデアを言葉にして、実現へ向けたステップを描きます。参加者同士の交流の時間もあります。第2日目 ワークショップⅠ
1月17日(土)14:00-18:00
先行事例の共有や、参加者同士の対話を通じて、多様な視点に触れながら、地域での実践を学び、自身のアイデアを具体的にブラッシュアップしていきます。第3日目 ワークショップⅡ
2月7日(土)14:00-18:00
ワークショップIに続いて、アイデアのブラッシュアップを実施。最終回でのエキシビションに向けてトライアルの内容を具体化します。第4日目 エキシビション
3月7日(土)10:00-18:00
コウカシタパークをフィールドに、店舗・ワークショップ・展示などのトライアルを実践。アイデアをカタチにすることで、各プロジェクトを加速するための学びを得ます。