福祉とは?弱さを変える映画監督
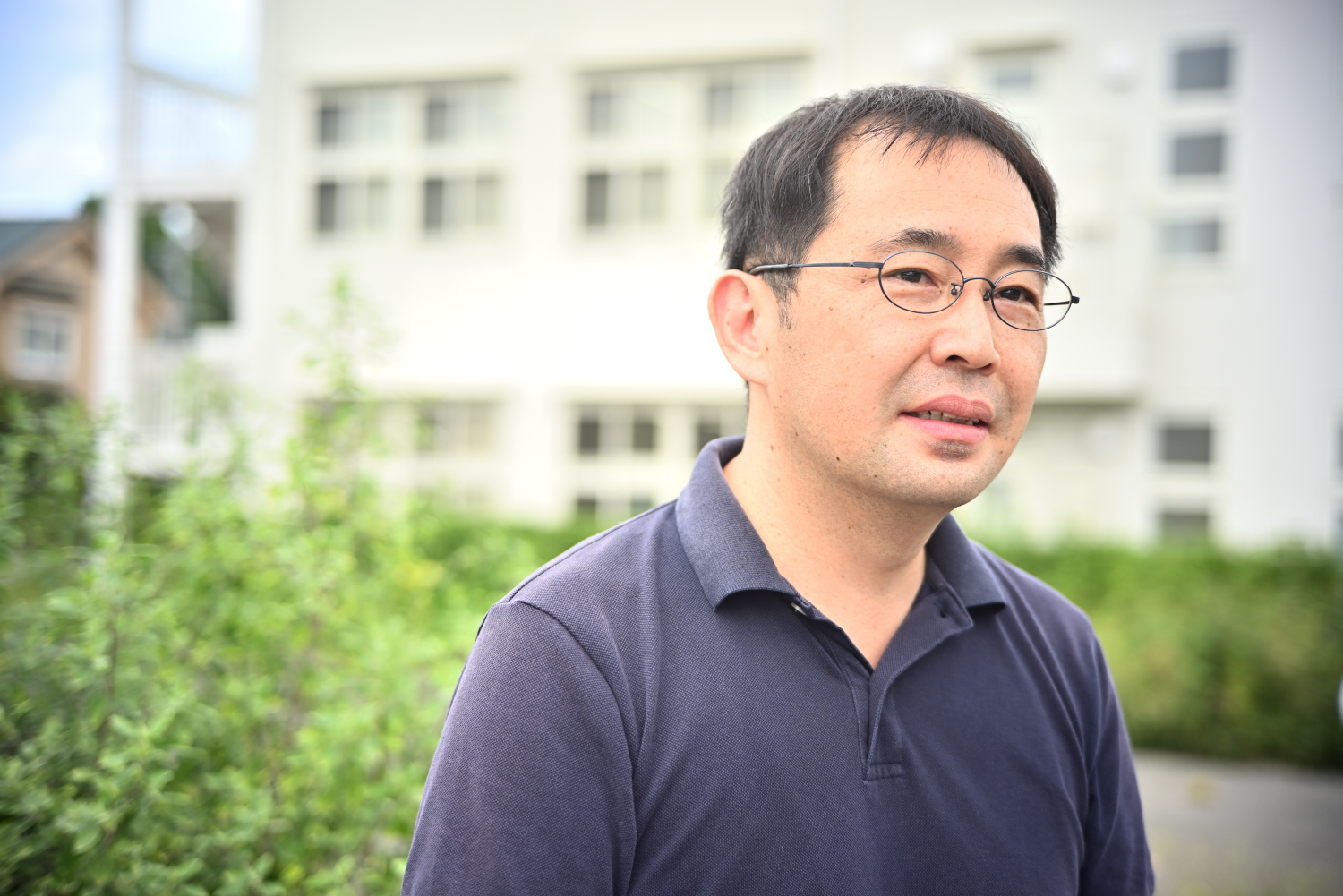
障害のある人と接するときに生まれる、戸惑いやためらい、葛藤。率直に言えばそうした感情から、隣にいるのに身近にいないと感じさせる“無関心”が生まれているのでしょうか。
「なぜこんな大変なことやってるんだろうってね、自分でよく思います。僕、いい映画を作りたいだけで、気がついたらこうなっていたんです」。そう話すのは、2020年、“弱さにある希望を表現する映像メディア”として「にじメディア」を立ち上げ、2025年からは一般社団法人にじメディアの代表として活動する齋藤一男さん。すべての人が持っている“弱さ”こそが希望であると発信する、齋藤さんの考えを聞きました。
これからの福祉を考える
東久留米市にある施設「さいわい福祉センター」を会場に、この7月から「あなたとわたしワークショップ#3」がはじまりました。映像プログラムに集まったのは、知的障害のある11名の参加者。全4回約4ヶ月をかけ、演者もしくは制作者として、“得意や好き”を活かしたショート映像作品をつくります。制作ステップを説明する時間、にじメディア代表の齋藤一男さんは問いかけます。
「こういう制作の流れで、みなさんどうですか?」
この日、部屋の中からは「はい」も「いいえ」も返ってきません。じっと齋藤さんを見つめている人、体を揺らしながら、付き添いの家族のそばでぬいぐるみをさわっている人。彼らの表情や動きに目をやりながら、齋藤さんは少し間を置いて説明を続けます。話す内容も話し方も、障害のない人に向けるものと変わらないように聞こえます。想像するまでもなくそこにあるコミュニケーションの難しさ。齋藤さんは、なぜ問いかけるのでしょうか。

「勝手に決めるのは楽です。だけど、僕たちがしたいのは楽しむことで、機械的なルーティンで楽をすることではありません。主催者が“なあなあ”になれば、その雰囲気は絶対伝わってしまう。僕はかなり意識して、自分が楽しみ、そして必ず彼らにも問いかけます」
福祉作業所の非常勤スタッフとして勤務したこともある齋藤さん。いわゆる福祉の現場に身を置く中で、人の幸せを追求することが福祉だとすれば、サービスを受けるかどうかに関わらず、福祉はすべての人にとって身近であるべき概念なのではないか、と思うようになったといいます。にじメディアでは、障害の有無を超えて、一人ひとりの幸せや楽しさを追求しようとしています。
「実際、判断してもらうのはほぼ難しいです。それでも、こちらの熱量は温度感となって彼らに伝わるはず。僕は長年、映像制作の仕事をしてきて、にじメディアもその一環だと捉えています。障害のある人を取り巻きがちな、憐れみのような雰囲気をつくるのは絶対に嫌だし、僕自身が感じているものとも違う。一緒に制作をする仲間という感覚で、できる限り、発言したり思いを表明できる環境をつくりたいです」

強いものが勝つ世界
大学卒業後は、映像業界にどっぷりと浸かっていた齋藤さん。ドラマなどフィクション作品の制作現場で汗を流し、30代で「ロゴスフィルム」として独立。それまでの人生、福祉や障害者に関する分野への興味関心はゼロだったそう。転機は独立後、映像と並行してできる仕事を探していたとき、偶然、福祉作業所の非常勤スタッフ募集を見つけたことでした。
「働きはじめて、すぐ辞めたくなりました。まったく未経験でしたし、すごく大変で。でも、作業所にいる間に何というか、『(障害のある)彼らは人間として一番大切なものを持ってる』という気持ちになったんです。自分が何をしたいかという、シンプルな感情を持っている。僕にもかつてはあったのに、変なプライドやしがらみで見えなくなっていたんだと、彼らと過ごしている間に思い出して。この気づきってすごく大事なことで、色んな人に知ってもらう必要性があるんじゃないかと感じました」
作業所の中だけの関係性では、まず自分にとってもったいないと考えた齋藤さんは、「学びとして何か活動ができたらいいな、ひいては一緒に働くこともできたら」という夢を描くようになりました。
その後、齋藤さんのもとに、障害のある人とともに映像作品をつくる機会が何度かめぐってきます。
「一番最初につくったのは、僕が企画して、知り合いの自閉症の男性に演者として出てもらった映画です。2010年くらいのことです。人が好きそうだなというのは伝わってきていて、僕の直感では、演者に向いていそうな気もしたんです。『作品として成立しそうだぞ』という制作者としてのイメージも膨らんだ。秘めている何かを感じたと言ってもいいですね。それで、出てもらえたら面白いなとお願いしたら、応えてくれました」


齋藤さんと彼がはじめた初めての映画制作は、約2年間にわたりました。
「知的障害があると、色々な理解に時間がかかるので、彼の自主性を保つためにゆっくりやっていくことにしました。枠を決めて進めるより、彼のやりやすいように動いてもらう方がスムーズに進みましたね。この経験があるからこそ、今のにじメディアがあります」
当時は、プロジェクトや事業にすることをまったく想定していなかったそう。しかし、作品をつくるには年単位の時間が必要で、作業のボリュームも大きい。毎回そのやり方で複数本つくろうとすると、齋藤さんももたず、経済面でもやっていけない。方法を思案した末にたどり着いたのが体験形式のワークショップ。その運営母体として、にじメディアが誕生しました。
「障害のある人と一緒に映像をつくりたいと思った理由も、僕が映像業界から独立した理由も、考えてみると同じなんです。映像業界は、強くて、続けられる人だけが生き残る世界。才能や思いよりも、体力とか、営業が得意とか、人付き合いの上手さが勝つ場面をたくさん見てきました。違和感を抱き続けていた僕が福祉作業所で働いた偶然は、すごく意味があることでした。僕がしたいのは、弱さや生きづらさを抱えた人と一緒に、いい映画、映像作品を作ること。流れのまま進んでいたら、今の事業になったんです。僕、キャパシティも小さいのに、大変なことになりました(笑)」

1人いれば、空気は変わる
キャパシティを超えて、事業を育てることに奔走するこの数年。齋藤さんを突き動かし続けるのは、心に深く刻まれた“無関心”だと教えてくれました。
「映像業界どっぷりだったころ、仕事に忙殺されて、自分にとって大事なものにさえ無関心になっていました。誰でもそういう経験ってありますよね。後悔したり、取り返しのつかない経験をすることになってしまったり…。いくら人から聞いても、実際に自分がその状況に陥るまでわからない。映像も同じで、見ただけじゃ人はそうそう変わらないからこそ、僕が一緒に制作する作品は、スクリーンの中の本人と会っている気がするくらい、とにかく体感できる映像を意識しています」
作品をつくったその先には、どんなことを期待しているのでしょう。
「無関心だった彼らに目が向き、『友達になってみたいな』とか『一緒に働いてみたい』とか、そう思ってくれる人が増えるといいなと思います。1人そう思う人がいるだけで、企業でも地域でも、空気って変わります」
障害のある人と関わりながら営む事業は、ときに、世間からの厳しい目線にも晒されます。お金儲けに利用しているのではないか。本当に彼らに主体性はあるのか。つくった作品は、彼らのものと言えるのか。
「お金を取るのがとても怖いです。お金儲けだと思われるんじゃないかという不安がつきまとう。でも『事業をする上で一番優先する動機はお金儲けではない』という否定が自分の中に強くあるからこそ、世間の問いにも明確に答えられます。僕にとって重要なのは、映像制作を通してみんなで楽しむことなので、例えば、社会一般の価値観で評価される映画祭の賞は取りづらいでしょう。目に見えないことをしてるので、評価しづらいし、されづらいのは課題でもありますが、固定化された物差しでは測られたくはありません」

「一番最初に映画をつくった自閉症の男性とは今でも交流があって、変化がとても興味深いんです。彼は言葉でしっかり表現できるタイプではないので、僕の想像の域を出ませんが、自己肯定感が上がってちょっと自信がついたのかな。映画に出たことが理由なのかわからないのはとても悔しいけど、でも、きっと影響はあるだろうなって信じたいです」
障害のある人がはじめる複業
「今、障害のある人の複業ということを考えています。作業所に所属はして、依頼が来たときに一緒に映像制作をするとか。こちらの体制を整えなければなので、少し先の話ですが」
齋藤さんが構想を練る背景には、障害のある人が特別支援学校を卒業すると、大半の人が仕事をする道に進むという現状があります。
「特別支援学校ではない高校なら、7、8割が進学するじゃないですか。同じように、自分で考えて、自分の責任でやっていく、そういう経験をできる場をつくれたらいいなと。僕らは表現の専門学校のような場をつくれないかと考えています。映像をつくったり絵を描いたり、ドラムを叩いたり…。そういう好きなことをただの趣味ではなくて、実益もともなった活動にできれば、障害のある彼らが生きていくための収入に還元できる。本人はたぶん、楽しいことをできれば幸せだと感じてるとは思うので、僕の勝手な『もったいないな』という気持ちですけど、そうやって複業への道筋をつくれたらいいなと思っています」
障害のある人が大人になったとき、できるだけ自立しながら、好きなことも続け、どのように暮らしていくのか。可能性を広げようとすると、制度や環境がハードルとなっている現実もあります。
「僕たちのワークショップでは、本人ではなく、親御さんが興味を持って参加されるケースが多いんです。その点は、『開催する意味が本当にあるのか』という自問自答が続いています。一方で、福祉業界で働いている人がよく言うのは、『彼らが知らないままでいた方がいいこともあるよ』という話。厳しさを知っているからこそ、可能性を広げてもかえってつらいだけだ、という空気があります。でもやっぱり、僕は違うと思うんです。同じように可能性を諦めたくない親御さんも多いと思います。そもそも、利用できる場所やサービスが限られているので、それを利用せざるを得ないし、それすら、探して申し込んで…と大変。だから欲張れないっていう現実があるんです」
障害があっても、可能性を取り上げない。そのためのプラットフォームづくりを目指し、クラウドファンディングへの挑戦も決めました。障害の有無というカテゴライズではなく、フラットな視点で接し合える場をつくるため、福祉にまつわる給付金などの支援金をこのプラットフォーム事業には一切受けないと決め、賛同者を探しています。
「障害のある人の生き方、働き方を考えることで、弱さとか生きづらさ、これからの社会のあり方を考えることができるんじゃないかと思っています。そういう思いもあって、僕は福祉の枠組みではないところで実現したいんです」
「すべての人は本来弱さを持っていて、その弱さを自覚することが強さであり、希望であるという価値観を映画を通して表現していきたい」。齋藤さんがにじメディアに掲げたメッセージが、また一歩、実現に近づこうとしてます。(國廣)


プロフィール
齋藤一男
映画監督、プロデューサー、社会教育士。一般社団法人にじメディア代表理事、ロゴスフィルム代表。大学卒業後、映画映像の制作を生業としながら、独立以降は障害福祉の仕事も並行して行う。2020年12月、にじメディアを始動し、2025年4月には制作委員会を法人化。“弱さ”や“生きづらさ”をキーワードに、主に障害のある人と協働で進める映像制作のほか、ワークショップ、インクルーシブな学びの場「にじのば」、上映イベントなどを開催。